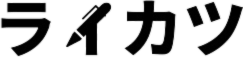2025年9月1日:追記
文賢の初期費用(税込 11,880円)が、なんと9/1より無料になりました!
- 『文賢』ってどのくらいの費用がかかるの?
- 価格(料金)の妥当性を教えて!
こういった悩みをお持ちの方のために、文賢の価格の妥当性(+元を取る方法)がわかる記事を書いてみました。
先に結論を書いてしまうと、文賢の価格は「妥当」です。
実際に、僕は文賢を導入したことで文章作成にかかる時間が半分以下になり、収益も大幅にアップしました。
ざっくり計算すると「1記事あたり3000円」くらいの導入効果が得られた計算になります。
人によって効果は異なると思いますが、決して損はしないはず。ぜひこの記事をチェックしてみてくださいね。
※そもそも「文賢って何?」という方は、↓の記事で詳しく解説していますので、よろしければこちらをどうぞ。
-

-
「文賢は使えない」評判は本当?損をしない使い方7選【レビューあり】
続きを見る
更新費用が最大15%off!
今ならライセンスのまとめ買いで最大15%お得になる『文賢』がおすすめ。個人の方は1ヶ月分無料になる「年払い」が狙い目!
こちらをチェック!» 文章作成アドバイスツール【文賢】![]()
スポンサーリンク
文賢の価格は「妥当」です。
実際に使っている感想として、文賢の価格は「妥当」どころか、かなりお得な料金設定だと思います。
ただし、その恩恵が受けられるのは、以下の2つに当てはまる人だけです。
- 人に読まれるための文章を書いている人
- 給料や原稿料など、「文章」が具体的な収益に直結している人
これらに当てはまっていない人は、わかりやすいメリットは感じられないかもしれません。
その理由を説明する前に、まずは文賢の価格についておさらいしてみましょう。
文賢の価格(※実際にかかる費用)
2020年時点での文賢の価格は、以下になります。
- 初期費用:10,800円(税込11,180円)
- 月額費用:1,980円(税込2,178円)
まあ、ぶっちゃけ高いですよね。2,178円あれば、NetflixとSpotifyに入れますし。
※まとめ買い割引もありますが、今回の記事は個人を対象にしているので除外します。
競合ツール(Just Right!6 Pro)と比較してみた。
この価格が、はたして高すぎるのか。有料の文章校正ツールとしてよく比較される『Just Right!6 Pro』と比べてみました。
| 文賢 | Just Right! | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 11,180円 | 36,940円(※1) |
| 月額費用 | 2,178円 | 0円 |
| バージョンアップ費用 | 0円 | 27,720円 |
| 対応OS | Mac/Windows | Windows |
| スマホ・タブレット対応 | タブレット可(※2) | 非対応 |
※1:Just Right!6 Proの定価は51,700円ですが、4年前の商品なので現在はこのくらいで買えます。
※2:公式では明言されていませんが、手持ちのiPad mini5で動作確認済み。
料金シミュレーション
料金プランがわかりにくいので、実際に1〜2年間ツールを利用した際の料金を比較してみます。
| 文賢 | Just Right! | |
|---|---|---|
| 1年間の総費用 | 37,316円 | 36,940円 |
| 2年間の総費用 | 63,452円 | 64,660円(※) |
※Just Right!は1年以内に新バージョンが出る可能性が高いので、バージョンアップコストを加算しています。
こうして比べてみると、両者にそれほど大きなコスト差はないので、文賢の価格は文章校正ツールとしては標準的といえます。
3年、4年と長く使っていけば、Just Right!のほうが徐々に割安になっていきますが、それならば1、2年とりあえず文賢を使ってみてから、Just Right!の新バージョンが出たタイミングで切り替えを検討しても、それほど損はないかと。
結論:元が取れない人は、物書き失格。
ここまで読んだ方は、
年間3万円弱というコストに、文賢は釣り合っているのか?
という疑問が浮かんでくるかと思います。
結論から言ってしまうと、(文賢に限らず)文章校正ツールのコストが回収できない人は、プロの文章書きとして失格だと思います。
元が取れない=文章校正・推敲に手間をかけていない
文章校正ツールは、文字通り文章校正作業をソフトウェアが代行してくれるツールです。
つまり、文賢の元が取れないという人は、文章校正・推敲作業を手間をかけていない(おざなりにしている)人ということになります。
はっきり言って、これはプロの文章書きとして失格です。
プロの作家で、推敲してないひとなんて(たぶん)いません。原稿を編集部に送るまでに、何度も何度も読み直して練ります。その原稿が雑誌に載る際には、事前に「ゲラ」で確認し、さらに推敲します。雑誌に載った原稿を単行本にするとなったら、またも「ゲラ」を複数回やりとりし、気が遠くなるほど推敲します。その単行本が文庫化されるとなったら(以下略)。
それぐらい、推敲は重要です。書いた原稿を読み直しもせず投稿するなんて、「深夜に書いたラブレターを教室でまわし読みされる」なみの恥辱だと思ってください。
第1回「小説とは、推敲を重ねて初めて完成するもの」と肝に銘じるべし。|小説を書くためのプチアドバイス by三浦しをん|集英社Webマガジンコバルト
上記は小説を例にしていますが、ネットメディア・ブログの記事や論文・レポートなどでも変わりません。
校正・推敲の重要さは、真剣に文章を書いたことがある人ならば、骨身に染みるほど何度も実感しているはず。
まったく感じていなかったとしたら、マジでヤバイです。
文章校正・推敲にどれくらい時間をかけてる?
例として、僕が文章(4000文字)を書く際にかけている時間を計算してみます。
- 構成:30分
- 執筆:90分
- 校正:150分 ←文章校正ツールの出番
こんな感じ。「構成:執筆:校正」が「1:3:5」といった割合ですね。
※ちなみにこの数字は文賢導入前のもの。これがどのくらい時間短縮できたのか、については次項で解説します。
文章校正・推敲にじっくり時間をかけている人ほど、文賢導入の費用対効果は高いです。
あなたは現在、どのくらい「文章校正」に時間を使っていますか?
具体的な文賢の時間短縮効果(使い方2パターン)
お次は、文賢を使って実際に作業時間を短縮し、収益アップを実現するための方法を、自分で文章を書く場合(ライター・ブロガー)と、人が書いた文章をチェックする場合(編集者)の2パターンに分けて解説します。
ライター・ブロガーの場合
僕が実際に4000文字程度の原稿を書くケースを例にして説明します。
1.構成→原稿執筆(90分→60分)
執筆前の構成作業に30分ほどかけているので、実際に文章作成にタイピングしていた時間は60分くらいでした。
もともと執筆時間は短いほうでしたが、文賢導入後は文章の巧拙を意識しなくてよくなったので、長文タイピングやライブ変換などのテクニックを駆使して文章作成のスピードが格段に速くなりました。
2.読みやすさチェック(30分→5分)
以前は読みやすさ・わかりやすさの基準があいまいで、直したり戻したりを繰り返していました。
文賢導入後は、「アドバイス」ツールにあらかじめチェックリストを登録してあるので、各項目に沿ってざっと読み直すだけでOKになりました。
3.表現チェック(0分→30分)
以前は、こういった表現のブラッシュアップというものをあまり意識していませんでした。
文賢導入後は、「文章表現」ツールが言い換えられそうな文字列をハイライト表示してくれるので、サジェストされた言い回しを参考に、より印象的な表現に直していくという作業が新たに加わりました。
この作業を行うだけで、文章のクオリティは驚くほどアップします。
4.表記ルール統一(60分→10分)
以前は、表記ルールのリストに沿って一つひとつの文字列を検索し、直していました。
文賢導入後は、「推敲支援」ツールが漢字・ひらがなの開き/閉じといった表記ゆれを自動抽出してくれるので、それに沿って直すだけでOKです。
仕事のクライアントによっては、その会社独自の表記ルールを設けているところもあるのですが、そういったものも登録しておけます。
5.誤りチェック(30分→10分)
単純な誤字脱字やタイプミス、表現上の誤りなど、以前は何度読み返しても見落としが見つかるため、ストレスでした。
文賢導入後は、「校閲支援」ツールがこういった誤りを自動で見つけてくれるので、非常に助かります。こういった部分はツールの真骨頂ですね。
僕の場合、この工程は別のツール(ATOKクラウドチェッカー)を組み合わせて使っています。
6.最終チェック(30分→5分)
文章校正ツールといっても完璧ではないので、必ず最後に目視でのチェックも入れるようにしています。
まあ、この時点で致命的なミスが見つかることはほとんどないので、本当に念のため、といった感じですね。
結果:4時間→2時間
トータル時間が半分になっただけでなく、表現を練り直す時間を新しく設けたことによって、質も格段にアップしたので、実際の数字以上の効果があったと言えます。
次に、作業時間が半分になるメリットを、ライターの報酬を基準に計算してみます。
1記事6000円(文字単価1.5円)で計算すると、同じ時間で2記事=12,000円の仕事ができる計算になります。
これはあくまで僕のケースです。仕事を獲得するコストなども加味するとそのおよそ半分くらい、1記事あたり3,000円くらいが、文賢導入による収益増効果といっても皮算用でないかと思います。
1記事書けば(増やせば)月額料金の元が取れてしまうと考えれば、むしろ格安という僕の意見にも同意してもらえるのでは?
今回は標準的なボリュームの記事を例にしましたが、表記ルールの統一や誤りチェックといった作業は、文字数が多くなればなるほどツールの短縮効果が発揮されるので、さらに効率が良くなりますよ。
編集者の場合
メディア運営者やサイトオーナーなど、記事を外注ライターに書いてもらうケースも考えてみます。
文章チェック(60分→5分)
あらかじめ全体のおおまかな構成を決めておけば、内容のチェックだけで済みます。
以前は、基本的に自分で書く場合↑と同じ工程で文章をチェックし、修正をお願いする場所をメモしていました。
文賢導入後は、チェック画面をスクショするだけなので、驚くほど時間が短縮できました。
リライト(150分→60分)
自分でリライトする場合は、↑の2〜6の作業を行う感じです。
文賢導入による時間短縮効果は言わずもがなですね。
隠れたメリットがあったり・・・。
修正依頼をするときも、以前はあからさまなミス以外はなかなか指摘しづらかったのですが、ツール越しだと遠慮なくお願いできるようになったというのも、大きなメリットと言えますね。
『文賢』唯一のデメリット【苦言です】
価格の妥当性はじゅうぶんにわかったけれど、やっぱり自分で使ってみてから判断したい。そう考える人も中に入るでしょう。
しかし、残念ながら文賢は現時点で試用版のようなものが存在していません。
体験会は定期的に開催されているようですが、場所や時間が限られてしまい、なかなかハードルが高いですよね。
システム的に無料体験版が難しいのかもしれませんが、一週間以内の返金保証とかあればいいのになぁ・・・なんて思ったり。
まとめ:元を取れるかどうかは、あなた次第。
一見すると、価格が高く思えてしまう文章校正ツール『文賢』。
しかし、文章で本気で稼いでいこうと考えている人なら、決して損することはないはずです。
※それ以外の方は無料ツールで充分なので、↓の記事を参考に使いやすそうなものを探してみてください。
-

-
【無料/有料】現役ライターおすすめ日本語文章校正ツール9選【比較あり】
続きを見る
とりあえず、自分がいま現在、文章チェックにどれくらいの時間をかけているか?を計算してみることから、まずは始めてみるのがおすすめです。
文章チェック(校正・推敲)にかけている時間が極端に短ければ、文章作成のやり方自体を改善しましょう。
文賢の導入はそれからでも決して遅くありません。
晴れて文賢を導入することになったら、今回の記事のように「これまでどれくらいの金額を損をしていたのか?」を計算すると面白いかもしれません。
きっと、びっくりするはずですよ。
更新費用が最大15%off!
今ならライセンスのまとめ買いで最大15%お得になる『文賢』がおすすめ。個人の方は1ヶ月分無料になる「年払い」が狙い目!
こちらをチェック!» 文章作成アドバイスツール【文賢】![]()