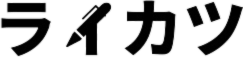- メールや企画書の文章が思ったように書けなくて、仕事が上手くいかない。
- もっと文章が上手くなって、ビジネスで活躍したい! でも、社会人に必要な文章力ってどんなスキルなのかよくわからない・・・。
- 文章力がない社会人でもうまく書けるコツやトレーニング法を教えて!
こんな悩みをお持ちのあなたのために、仕事で役立つ文章を上手く書くコツについて解説します。
結論から先に書いてしまうと、社会人で「文章力がない」と言われてしまう人は、
「文章のゴール」がはっきりしていない(もしくは間違っている)
これが主因であるケースがほとんどです。よって、文章を書くたった1つのコツとは、
ポイント
文章のゴールを明確にしてから書く
以上になります。
「そんなの当たり前じゃん」という方も、実は文章のゴールを履き違えて(勘違いして)いたりします。
注意ポイント
文章のゴールは「伝えること」ではありません。
ギクリとした方は、ぜひ以下に目を通してみてください。
このたった1つのコツさえ覚えることができれば、語彙力や表現力が足りなくても、本当の意味で「良い」文章が書けるようになりますよ。
スポンサーリンク
「文章力がない」とはどういう意味?(文章力とは?)
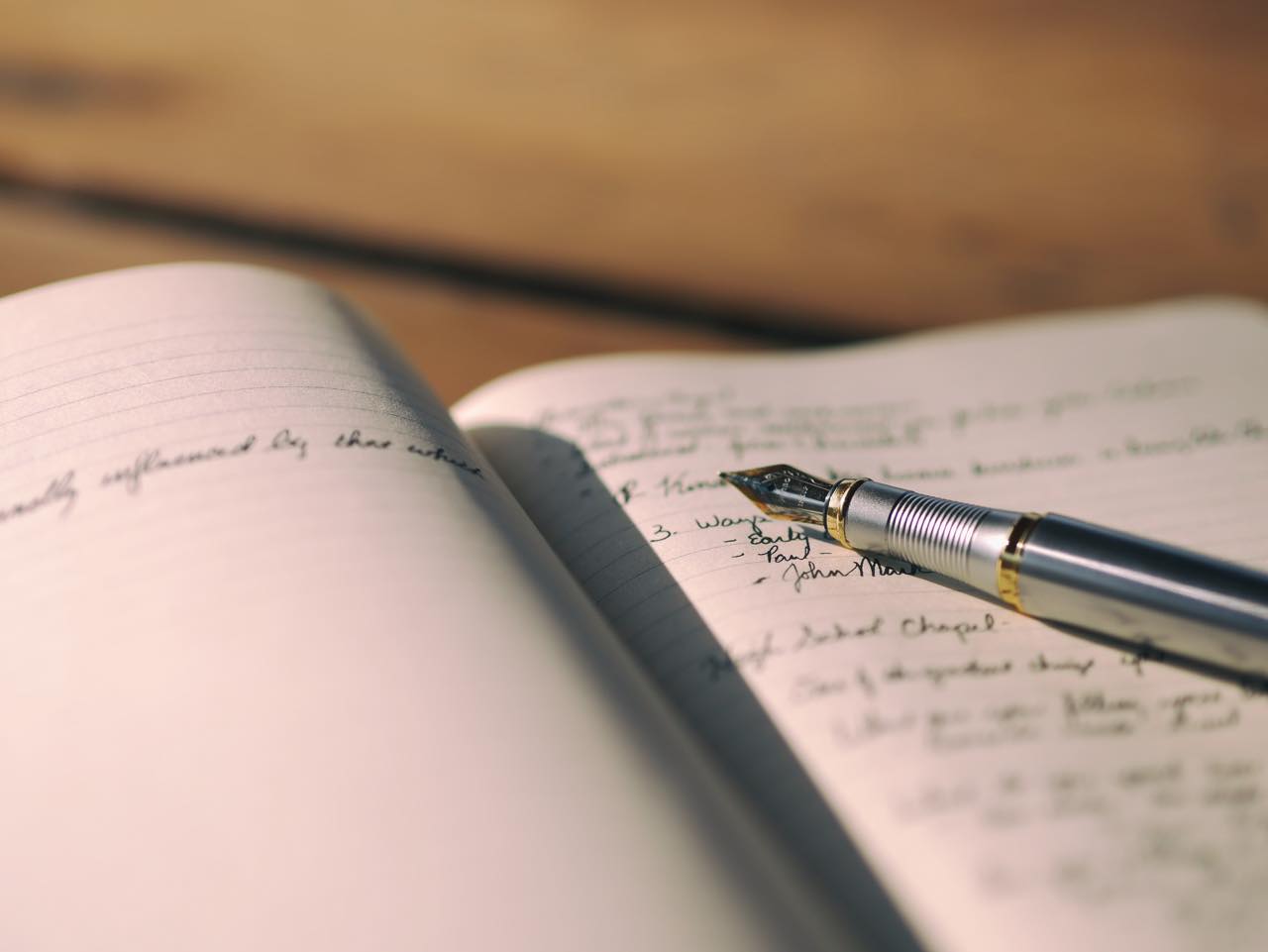
文章力がない人の特徴4つ
文章力がない=語彙力・表現力がない
上記のイメージを持つ人が多いようですが、これは間違いです。
語彙力も表現力もあるに越したことはありませんが、ないからといってイコール文章下手とはなりません。
社会人にとっての「文章力がない人」というのは、以下の4つの特徴を持っています。
- やたら文章が長い
- 難しい言葉を使いたがる
- 話があちこちに飛ぶ
- 結論がはっきりしていない
要するに、何が言いたいのかよくわからない文章を書いてしまう人です。
以下で、それぞれの特徴について詳しく解説しますね。
やたら文章が長い
長文が必ずしも悪ではありませんが、冗長は厳禁です。
- 前置きが長い企画書
- 言い訳が多い報告書
心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
なんて思ってしまいますよね。
ほかにも、
- 余計な修飾語やまわりくどい言い回しが多い
- しかも、それらが効果的に生かされていない
ひどいものになると、一文に主語・述語が複数並んでいるなんてケースもあるので、注意が必要です。
難しい言葉を使いたがる
- 慣用句
- 四字熟語
- 専門用語
こういったものを多用しがちなのも、悪文を書いてしまう人の典型です。
語彙力や表現力に自身がある人ほど、この罠に陥りがちです。
知的に見せたいのかもしれませんが、はっきり言って逆効果です。
無闇矢鱈と散らばった難解な言葉の数々からは、書き手の不安や虚勢が透けて見えてしまいます。
話があちこちに飛ぶ
- 段落の前後がつながっていない
- 事実と感想がごちゃまぜになっている
- 補足説明が多い
こういった文章は読む側の手をいちいち止めてしまい、スムーズな理解を妨げます。
真面目で慎重な人ほど、なるべく漏れなく伝えようと、思いついたことをすべて書き連ねてしまいがちです。
その説明、本当に必要ですか?
結論がはっきりしていない
こんな印象を読み手に持たれてしまっては台無しです。しかし、この感想を耳にすることのなんと多いことか。
これら4つの特徴、大なり小なり心当たりがある方も多いのでは。
では、いったい何が原因でこんな文章を書いてしまうのでしょうか?
文章力がない原因はたった1つ
読みづらいわりに内容が薄い文章を書いてしまうそもそもの原因は、冒頭でも書いたとおり、
文章のゴール(目的)が明確でないから
これに尽きます。
書き手が文章のゴールをしっかりと理解していないから、書くべき情報の取捨選択や構成もはっきりとせず、冗長で支離滅裂な文章になってしまい、結論もはっきりしないという事態に陥ってしまうのです。
文章力がない(文章下手)=頭が悪いではない。
文章が下手な人は、頭が悪いというイメージを持つ方も多いようですが、これも正しくありません。
文章力がない=書く前に文章のゴールを明確にしていない
こういった原因に、頭の善し悪しはあまり関係ありません。
※本当に頭が良い人の中には、書きながら本質にたどり着いたうえで、文章全体も上手にまとめあげるというウルトラCをやってのけたりしますが、そんなことができるのはごく一部の天才だけです。ご注意を。
「文章力」というものの実態についてなんとなく理解できたところで、いよいよ上手い文章を書くためのコツについて解説していきます。
文章が上手くなるために覚えるべきたった1つのコツ

文章が上手い人の特徴4つ
文章力がない人の4つの特徴を逆にすれば、文章力がある人の特徴が見えてきます。
- 簡潔で一文が短い
- 平易な言葉を使っている
- 論理的で、話の流れがスムーズ
- 結論がはっきりしている
こんな感じでしょうか。
以下で、一つひとつ解説しますね。
簡潔で一文が短い
- 一文で伝えることは一つだけ
- 修飾語は最低限
コレが鉄則です。さらに、
主語と述語は、なるべく一文にひとつずつ
これができると、より読みやすい文章になります。
主語と述語が複数ある「重文」を使う際は、読点(、)で区切るようにするといいでしょう。
入れ子構造になっている「複文」は、なるべく使わないほうがいいですね。
文章を書く目的がはっきりしていると、それぞれの文の役割が明確になります。必要な情報だけを厳選して書くようにすれば、自然と一文一文が短くなっていきますよ。
平易な言葉を使っている
子供でも分かる言葉・表現を用いる
本当に賢い人が書く文章は、これが徹底できています。
たとえ文章を書く目的が「自分を知的に見せること」だったとしても(そんなケースは少ないでしょうが)、
- 専門用語やキザな言い回しが鼻につく文章
- 難しい内容をシンプルな言葉や表現でわかりやすく説明してくれている文章
どちらが知的に見えるかは、一目瞭然ですよね。
論点が明確で、話の流れがスムーズ
文章が目指すゴールがはっきりしていれば、後はいかにスムーズに読者をゴールまで導けるか?だけです。
効果的で目的を果たせる文章というのは、必要な情報が必要な順序で論理的に構成された、道筋がはっきりした文章です。
余計な脇道にそれたり、同じ場所を行ったり来たりしたり、まったく別の場所へワープしたりすることはありえません。
結論がはっきりしている
文章の目的が明確である=ゴールがはっきりしているということは、文章の結び(結論)があやふやでブレる心配もありません。
結論がはっきりとしていれば、文章の構成もその結論に説得力をもたせることに注力できます。
【結論】覚えるべきコツは1つだけ
以上から、文章巧者になるコツは、
ポイント
文章のゴールを決めてから書く
これ1つだけとなります。
たった1つのコツさえ守れていれば、自然と一文一文が簡潔になり、言葉も平易でわかりやすいものを選ぶようになり、論理的で結論へしっかりと導かれる文章を書くことができるようになります。
「文章の目的=伝えること」ではない
ひとつ注意が必要したいのが、
文章を書く目的を履き違えてしまう
という落とし穴です。
「文章を書く目的は?」と質問すると、
と答える人が多いのですが、これは半分正しく、半分間違っています。
なぜなら、「伝えること」は文章の役割として必須事項ではありますが、それ自体は「ゴール=目的」ではないからです。
- 企画書のゴール:提出した企画が採用されること
- メール挨拶文のゴール:相手に好印象を持ってもらい、以後の仕事をスムーズに進めること
このように、伝えたその先にこそ、文章が目指すべきゴールが存在するのです。
場合によっては、上記のさらに先の展開にゴールを据えるケースもあります。
報告書や議事録の類であったとしても、巧みな書き手は相手に自分が意図した印象を与えたり、思った行動をとってもらうようにと、文章の書き方を工夫しています。
目的を履き違えてしまうと、どれだけ時間をかけても、本当の意味で「良い」文章には決してなりません。
誰でもスラスラと文章が書ける5つのフロー
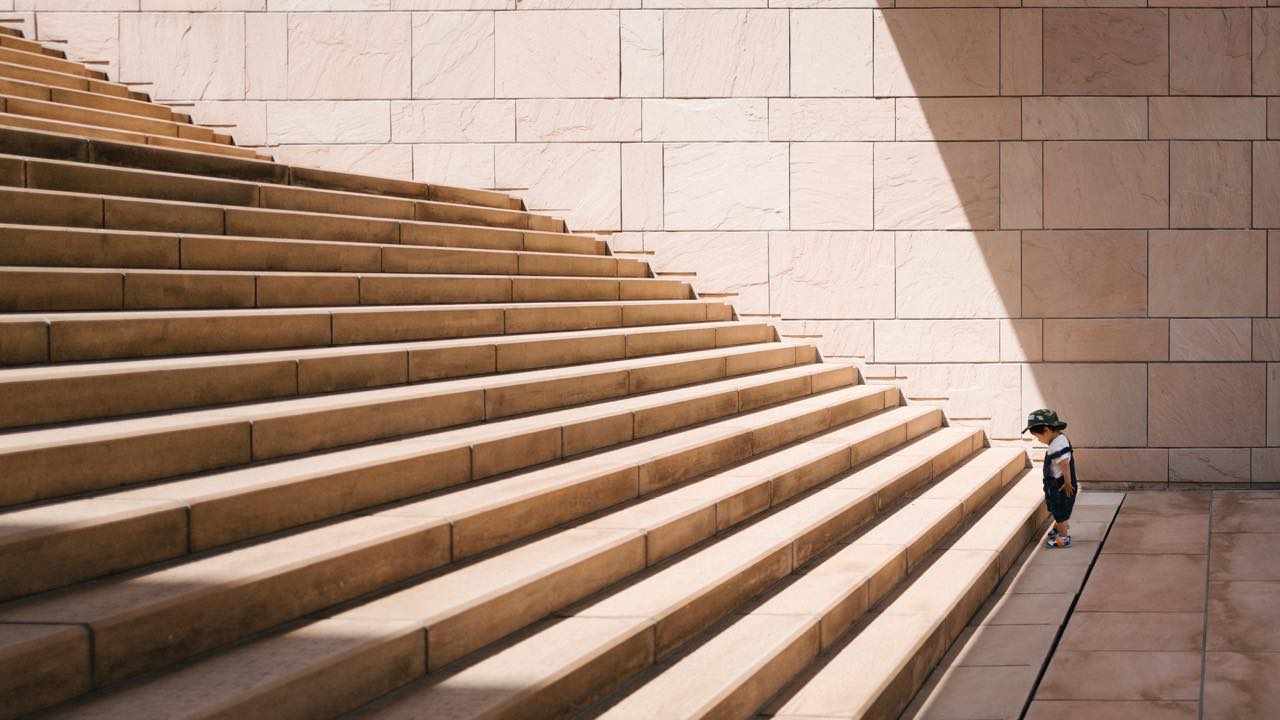
文章のゴールを決めさえすれば、あとは以下のフローに従って作業を進めれば、迷うことなく誰でも一定以上のクオリティの文章を書き上げることができます。
- 文章の目的を明確にする
- 情報を集め、分類する
- フレームワークに沿って構成を考える
- ひととおり文章を書く
- ツールを活用して推敲する
ポイントは、既存の文章フレームワークや便利な執筆ツールを徹底的に活用すること。こうすることで構成力不足や表現力不足を補うことができます。
-

-
文章が超わかりやすくなる「PREP法」とは?【使い方・トレーニング解説】
続きを見る
-

-
無料あり:日本語ワープロソフトおすすめ7選【Mac/Windows10】
続きを見る
-

-
【無料/有料】現役ライターおすすめ日本語文章校正ツール9選【比較あり】
続きを見る
文章力を磨く。毎日できるトレーニング法

今回紹介した「たった1つのコツ」さえ守れれば、必要最低限の文章は書けます。しかし、様々なスキルを身につけることで、さらに巧みな(効果的な)文章が書けるようになります。
文章力をアップさせるのに役立つスキルには、以下のようなものが挙げられます。
- 語彙力
- 読解力
- 情報収集力
- 構成力
- 要約力
- 比喩力
以下に、それぞれのスキルを鍛えるトレーニング方法を1例ずつ紹介しておきます。
語彙力を鍛える
語彙のストックを増やすには、読書が一番です。
普段から様々な文章に触れ、知らない単語が出てきたらその場で調べる癖をつけると、自然と言葉のバリエーションが増えていきます。
-
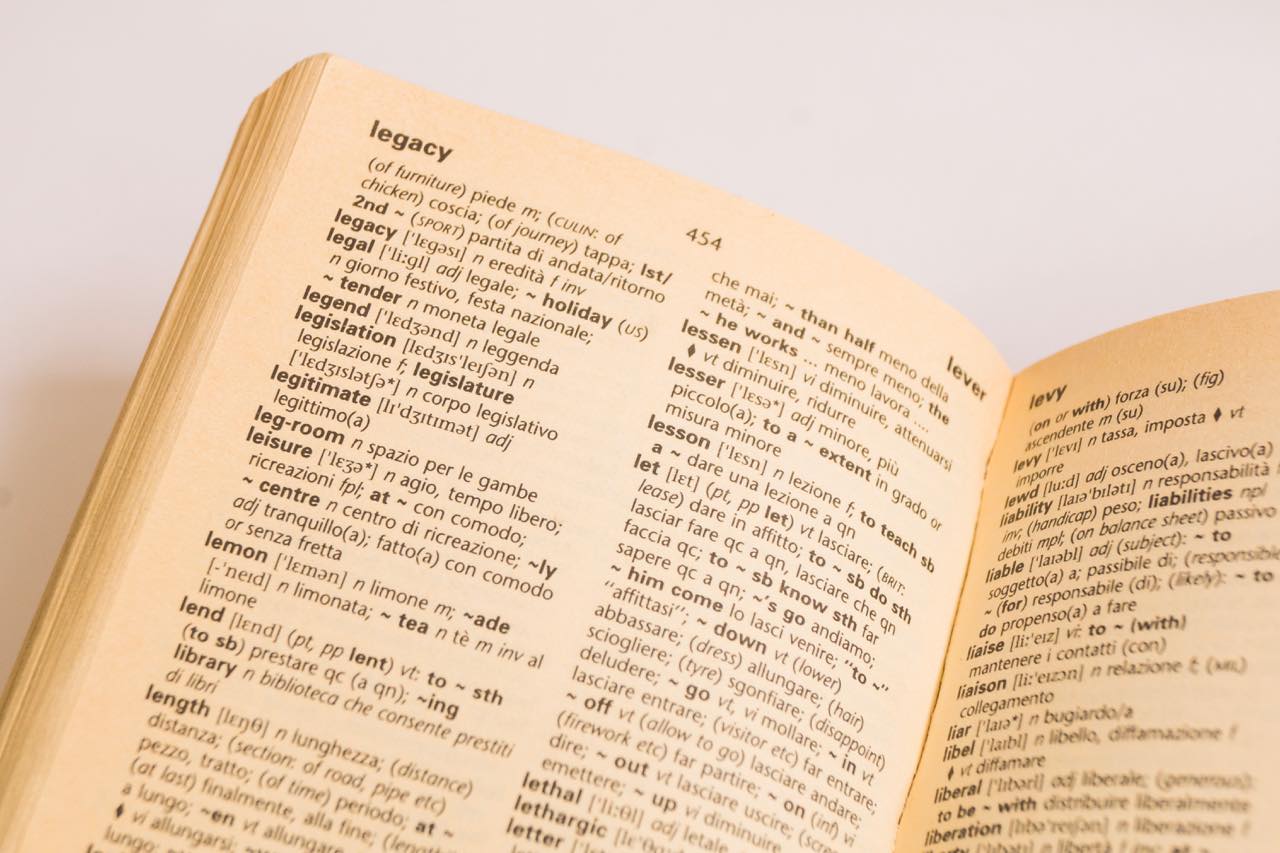
-
【脱ボキャ貧】語彙力を鍛える5つの方法(おすすめ本・アプリあり)
続きを見る
読解力を鍛える
これにも読書が有効です。
特に、未知のジャンルについて書かれた本を読むようにすると、自然と文章を読み解くスキルが磨かれていきます。
-

-
【文章が理解できない】読解力を鍛えるコツ+おすすめ無料アプリ5選【大人の国語】
続きを見る
情報収集力を鍛える
現在は、ネット検索で手軽に何でも調べられる時代ですので、気になったことは未知のままにしておかず、しっかり深堀りする癖を身につけましょう。
ネットやテレビのニュースを鵜呑みにするのではなく、様々な視点から分析してみたり、自分なりの考えを模索してみたりするのも、よい訓練になります。
構成力を鍛える
文章の構成力を鍛えるには、ブログを書くのが手軽でおすすめです。
先人たちによって様々な文章の型(フレームワーク)が開発されていますので、それらを活用しながら少しずつ構成力を磨いていくといいでしょう。
-

-
【初心者OK】いますぐ使える文章構成パターン+まとめ方のコツ17選
続きを見る
要約力を鍛える
これにはTwitterのつぶやきが向いています。
140字という制限の中で、いかに端的にかつ効果的に情報を伝えるか。あれこれと模索してみると、意外と奥の深い世界であることに気づきますよ。
-

-
【要約難しい】文章要約のコツ5+簡単な書き方【本・物語・小論文】
続きを見る
比喩力を鍛える
いわゆる「たとえ上手」になるには、巧みな比喩やキャッチコピーを見つけたらメモする習慣が有効です。
日常的に「比喩集め」を行っていると、自然と表現に対する意識も高くなるので、文章力全体の向上にもなります。
-

-
文章力が劇的にアップする修辞法(レトリック)10選【おすすめ本あり】
続きを見る
文章力を判定する資格:「文章検定」とは?
スキルを身につけるために「資格取得」を目指すというのも、モチベーションを保つ上で有効です。
文章に関する資格は、日本漢字能力検定協会が運営する「文章読解・作成能力検定(文章検)」があります。
小学校高学年レベルから専門職レベルまで、文章作成に関するスキルをトータルで試されるので、腕試し代わりに受けてみるのもおすすめです。
-

-
文章能力検定(文章検定)とは?試験に向けた勉強法や資格活用のコツ
続きを見る
目的別:文章力を向上させる本5冊
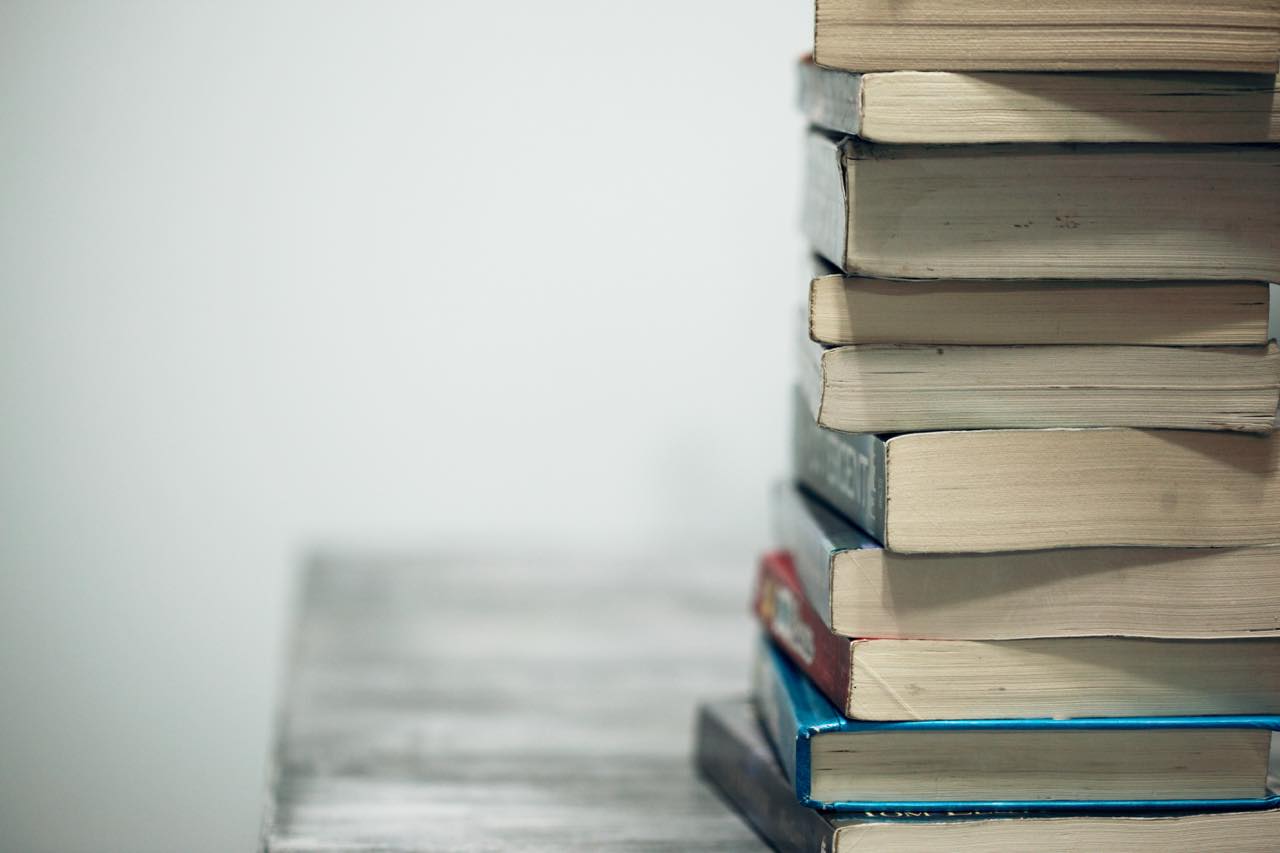
初心者向け
ロジカルライティングを身につけたい人
コピーライティングを身につけたい人
推敲スキルをアップさせたい人
ライターを目指す人
おすすめの本は他にもたくさんありますし、小説やエッセイなどの文章力を身につけるには、また違ったアプローチがありますが、今回は社会人向けのビジネスで役立つ文章力を鍛える本をピックアップしてみました。
まとめ:文章のゴールを決めてから書こう!

文章力がないのは、能力不足や頭が悪いからではありません。
たった1つのコツを守れているか、いないか。それだけです。
そのコツとは、何度も言いますが、
ポイント
文章のゴールを決めてから、書く。
これさえしっかりとできていれば、最低限のハードルはらくらくクリアできます。
後は、実際に文章を書く経験を積みながら、少しずつその他のスキルも身につけていけばOK。
じっくり腰を据えて、自身の成長を楽しむ気持ちで日々の文章を書いていきましょう。
-

-
【文章の書き方・完全解説】読みたいと思わせる文章を書く19のコツ
続きを見る