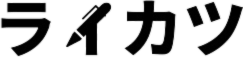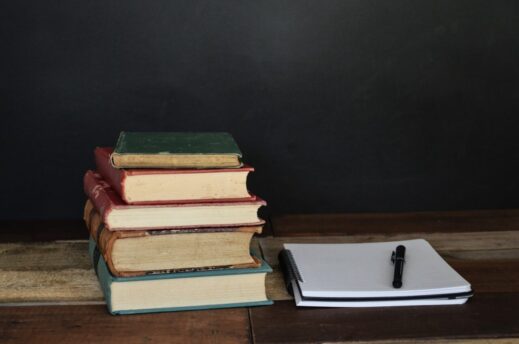「三題噺」で物語を考えろって、私は落語家じゃないんだけど・・・。
そんな悩みをお持ちのあなたのために、三題噺の書き方を詳しく解説します。
- 三題噺の書き方が知りたい。
- マスコミや出版業界に就職したいけれど、試験で「三題噺」が出るらしい・・・。物語なんて書いたことないけど?!
- 小説家を目指しているけれど、適当な物語のアイデアが思い浮かばない。文章トレーニングにもなる「三題噺」に興味がある。
- 初心者でも三題噺でスラスラと物語が書けるコツを教えて!
こういった方に役立つ情報になっています。
ネットで「三題噺対策」を調べてみると、出てくるのは「あらかじめ予定稿を準備せよ」というものばかり。
しかし、これではその場しのぎすらできない可能性が高いです(理由は後述)。
そこで今回は、どんなお題が出ても柔軟に対応できるよう、三題噺を使った物語創作テクニックのコツを解説。
- 【初心者OK】三題噺の書き方・コツ(手順解説&実例あり)
- そもそも「三題噺」って何?
- 三題噺のお題を出してくれるサイト・アプリ(お題メーカー)
内容はこんな感じ。
管理人は現役の作家でもあり、実際に三題噺を使って物語を書いた経験が何度もあります。
この記事を読めば、想定外のお題が出てアタフタすることなく、どんなテーマでもあっという間に物語が考えられるようになるはず。
「三題噺対策」を終えた後に取り組むべきことについても解説していますので、あなたはもう希望の職業への切符を手にしたも同然。ぜひ最後までご覧ください。
スポンサーリンク
【初心者OK】三題噺の書き方・コツ(手順解説&実例あり)

早速ですが、三題噺を使って物語を作るポイントを、実際に僕が作成した例文を交えてご紹介。
- 「SF(すこしふしぎ)」を考える
- 2つのお題を結びつける
- 残る1つのお題をつなげる
- 三行プロット(四行プロット)を書いてみる
- しっかりと「オチ」をつける
作業手順はこんな感じ。それぞれ詳しく解説しますね。
就活でもっとシンプルな三題噺の書き方を知りたい方はこちらをご参照あれ。
「SF(すこしふしぎ)」を考える
『ドラえもん』の作者として知られる故・藤子・F・不二雄氏は、SF(Science Fiction)を「すこしふしぎ」と呼んでいたそうです。
日常に入り込んだ、少し不思議な出来事・現象がもたらす物語・・・。まさに氏の世界観を的確に表現した造語と言えますね。
この「すこしふしぎ」という発想は、三題噺と非常に相性が良い考え方です。
一見無関係に思えるキーワードが組み合わることで生まれる「すこしふしぎ」。そんなアイデアから物語を考えてみましょう。
まずは2つのお題を結びつける
創作に慣れた方なら、いきなり3つすべてのお題を結びつける発想が出てくるかもしれませんが、初心者にはなかなかハードルが高いもの。
そこで、まずは2つのお題だけを選び、結びつきを考えてみましょう。
例えば、こんなお題が出たとします。※三題噺スイッチに出してもらいました。
- 毬(栗のイガ)
- 隠れる
- 椅子
この中から2つを選び、思いついたアイデアをいくつか書き出してみます。
- 巨大な栗の中には何が隠れている・・・?
- 栗のイガは、中の実を守るためにあるのではなく・・・。
- 椅子の下に隠れた子供が、自分にだけ見える。
- 家具に魂が宿っているとしたら、椅子の中には何が隠れている?
- 棘が付いていて座れない椅子。なんのため?
パッと思いついたものを書いてみました。どれも「すこしふしぎ」で、色々と妄想が広がりそうですね。
残る1つのお題をつなげる
お次は、書き出したアイデアと残った1つのお題を結びつけて、新しいアイデアを考えてみます。
- 巨大な栗の中には、何が隠れている・・・?→椅子?!
- 栗のイガは、中の実を守るためにあるのではなく・・・。→とある動物(虫)が椅子として使っている。
- 椅子の下に隠れた子供が、自分にだけ見える。⇢誰かが座ろうとすると、見えない棘が出てくる。
- 家具に魂が宿っているとしたら、椅子の中には何が隠れている?→人や動物ではなく・・・食べ物の霊。
- 棘が付いていて座れない椅子。なんのため?→家具職人の「とある意図」が隠されていて・・・。
こんな感じになりました。すでに物語の輪郭のようなものが見えてきていませんか?
三行プロット(四行プロット)を書いてみる
ここまできたら実際に書きながら展開を考えていきたくなりますが、いざ書き進めてみるとグダグダになってしまったり、支離滅裂な話になってしまうことも多いですよね。
そこでおすすめなのが、簡単なプロットを箇条書きにするというやり方です。
短編やショートショートなら数行でも充分。物語がどのようにはじまり、どう転がり、どう終わるのか。その構成をあらかじめしっかりと決めてしまうのです。
いわゆる「三幕構成」なら三行プロットを。日本人に慣れ親しんだ「起承転結」なら四行でプロットで。好みでやりやすい方を選んでかまいません。
試しに、↑の5つめのアイデアで三行プロットを書いてみました。
- 海外のオークションで、今は亡きとある名工が最後に遺した一脚の椅子が出品される。
- 人が座ろうとすると棘が生えてくる「からくり椅子」。人を拒絶するようなその存在と精緻なつくりは、孤高の存在であった職人の高い精神性を感じさせ、一躍話題となる。
- 実は、その椅子は家具職人が自分の体型にぴったり合わせて特注した「ツボ押し椅子」だった。
ついでに、3つめのアイデアで四行プロットも書いてみました。
- とあるリサイクルショップで見つけた、栗の木で作られた椅子。その下に、うずくまる子供の幽霊が見える。
- 試座しようとした客が不快な顔をしている。よく見るとうっすらと(自分にしか見えない)棘のようなものが椅子から生えている。
- 子供と目が合ったので、おそるおそる座ってみることに。するとなぜか自分には棘が生えてこない。
- 実は、自分は火事で亡くなったその子供の生まれ変わりだった。
「棘が生える椅子」という同じようなテーマですが、ずいぶんと趣の違う話になりましたね。
しっかりと「オチ」をつける
終わりよければすべてよし、なんて申しますが、物語のキモはやはり「オチ」にあります
特に、短編やショートショートにとって「オチ」は必須と言っても過言ではありません。
文章を書き出す前に数行プロットを考えるのも、この「オチ」をしっかりとつけるため。オチにふさわしい「フリ」を含め、物語の流れを常に意識しながら文章を書き進めましょう。
僕が作ったプロットも、この時点で一応オチは付いていますが、もうひとひねり欲しいという時は、
- 椅子を落札したのは、職人とまったく同じ体型をした彼の息子だった。
- 数年後、同じ椅子がふたたびそのリサイクルショップに並んでいて・・・。
みたいな結びを付け加えてみてもいいかもしれませんね。
あとは書くだけ
しっかりとしたストーリーの骨格ができていれば、後の作業は非常に簡単です。
すでに頭の中で動き始めている物語を思い浮かぶままに書き出していくもよし。数行プロットに肉付けするようにアイデアを書き足していき、最後に文章として整えるのでもよし。やりやすい方法を選べばOKです。
下手に凝った美文を書く必要はありません。特に筆記試験の作文の場合、採点する側は前述の構成力や即興力=物語そのものを見ているのであって、文章自体は一般的な作文力さえあれば充分です。
時間があれば、気になる言い回しや表現は後からでも直せます。まずは物語をしっかり完結させることを最優先しましょう。
おまけ:就職試験対策「三題噺」のシンプルな書き方(NG例あり)
マスコミや出版業界の就職試験に「三題噺」が出てきた場合、無理に凝った物語を考える必要はありません。
それよりも自己PRを兼ねて、自身のエピソードとからめて話を考えたほうがいいですね。
やり方は以下。
- 3つのお題ひとつひとつから思い浮かぶエピソードがないか考える。
- ひとつでも思いついたら、そのキーワードを軸に話を考える(2つあればベスト)。
- 残りのキーワードは「もしもあのとき◯◯があったら?」のような仮想テーマに使うといい。
話の流れ(構成)はこんな感じ。
- 起こった出来事
- そのときに自分がとった行動・理由
- 行動の結果・起こった変化
- 自身が学んだ教訓
- 「もし〜だったら?」(オチあり)
就活対策マニュアルなどでは、あらかじめ話を用意しておき、どんなお題が出ても強引にその話に当てはめてしまうといったやり方が推奨されていることが多いですが、個人的にはおすすめしません。
その理由は以下。
- 本人は気づかないかもしれないが、客観的に読めばあらかじめ話を用意していたのはバレバレ。
- 企業側は試験を通して、課題への対応力や咄嗟の発想力・構成力・文章力などを測っている。
- カンペ的な対処法は企業側が求めているものと合致しないため、評価が低くなってしまう。
カンペに気づかない、もしくは気づいてもスルーしてしまうような会社はちょっと・・・ねぇ?
事前に予習しておくなら話を作り込んでおくのではなく、記念の品や写真を見返しながら、そのときの感情をじっくり思い起こしたり、エピソードを共有する友人たちと思い出話に花を咲かせるといった感じにするのがおすすめですよ。
「三題噺」とは?

三題噺(三題咄:さんだいばなし)は、その名の通り、3つのお題から即興で話を作り出し、演じるもの。落語で用いられる形式の一つです。
あの名作落語『芝浜』も、三題噺(「酔漢」「財布」「芝浜」)から生まれたものなんだとか。
無作為に選ばれる3つの題目は、それぞれまったく関連性がない場合がほとんどであり、それらをどうやって結びつけ、一本の物語としてまとめるのか・・・。創作者の腕が試されます。
出版やテレビ等の業界で、就職試験に三題噺を使った作文が採用されている企業が多いのは、こういった業界に不可欠な構成力や即興力(対応力)といったものを試すのに、三題噺はうってつけだからでしょうね。
三題噺が文章力トレーニングに役立つ?

三題噺を使った創作作業は、文章力を向上させるトレーニングにもなります。
見た目だけの「美文」ではなく、もっと本質的な物語を組み立てる力や、一見無関係な物事を結びつけるユニークな発想力などは、文章を志す者だけでなく、クリエイティブな思考が必要となるあらゆる人に役立ちます。
プロの作家も、頭の体操代わりに三題噺を使って短い話を考えてみることもあると聞きます。いつもの自分からは生まれないようなアイデアが出る良いきっかけになるようですね。
とはいえ、ごくごく基本的な文章力が備わっていないとクリエイティビティなど無意味です。
詳しくは記事の最後で解説しますが、初心者ほど目を惹く真新しさばかり注目しがちなので注意しましょう。
三題噺のお題を出してくれるサイト・アプリ(お題メーカー)
ライトレ(iPhone/Android)

三題噺アプリとして最も有名なのがこのアプリ。
3つのお題をランダムで出題してくれる機能はもちろんのこと、文字制限や時間制限なども設定することができるので、作文の訓練に最適です。
アプリからSNS(Twitter、Facebookなど)に投稿することもできるので、面白い話が書けたらどんどん公開してみましょう。
三題噺スイッチ(Web)

↑で紹介した例文を作成するときに使ったのがこちらのWebアプリ。
特徴は3つのお題が「自然のもの」「概念的なもの・人物など・修飾語」「人間の作ったもの」という順番で出されること。必ずコンセプトが異なるキーワードが出題されるので、ミスマッチの妙がより楽しめます。
英語版もあり。
診断メーカー[三題噺](Web)

様々なWebアプリを無料で手軽に作成できる「診断メーカー」にも、三題噺を利用したツールがいくつか配布されています。
「乙女っぽい言葉」や「エッチなお題」など、特定のテーマに限定したお題を出してくれるものもあり。上記の2つも含め、色々と並行して使ってみると楽しいかもしれませんね。
-

-
【簡単】小説ネタが思いつかない・・・。おすすめお題メーカー(ネタ提供ツール)7選
続きを見る
「三題噺対策」の次にやるべき3つのこと

マスコミ・出版業界への就職を目指す方向け
三題噺が上手いだけでは、当然就職試験に合格することはできません。
- 最新ニュース(時事・エンタメ)のリサーチ
- 希望会社の出版物を確認
- 自身の性格・好み・価値観のおさらい
こういったこともしっかり行いつつ、総合的な対策を進めていきましょう。
おすすめのやり方は、図書館や書店などで気になる本を手に入れてじっくり読むこと。
どんな本に興味を持ち、どんな内容に惹かれ、どんな意見に反発を覚えるのか?
これらを読書を通じて考えることで、自身について深く知ることができます。
単なる就活としてではなく、自分を高め、さらに一皮剥けるためにひとつひとつ丁寧に取り組んでいきましょうね。
作家(小説家)を目指す方向け
いくらテーマを与えられても、いまいち上手に物語が作り出せない人は、作家としての基礎力が足りていません。
- キーワードから斬新なアイデア(コンセプト)を考えるコツ
- 魅力的なキャラクターのつくり方
- 物語構成の基本(三幕構成・起承転結など)
他にも小説を書くために学ぶべきことはたくさん存在します。
これらは有益な本やテキストがいくつもあるので、適宜活用しながら積極的にスキルアップしていきましょう。
ポイントは必ず物語を書きながら学習を進めること。書かずに指南本を読んでばかりではいつまで経っても実践的な知識やスキルは身につきませんからね。
まとめ
今回は、三題噺で上手に物語を書くコツを解説しました。
最後に、もっとも大事なことをひとつ。
物語そのものを考えるスキルよりも、いかに内容を正確にわかりやすく伝えるか?という文章力こそ、あなたは鍛えるべきです。
その理由は以下。
- どれだけ話が面白くても、その面白さの半分もうまく伝わらなければ無意味。
- 社会人にせよ小説家にせよ、アイデア力以前に基本的な文章力のほうがよっぽど役立つシーンが多いし、実際に求められている。
- 無理に奇抜(ユニーク)なストーリーを考えようとせず、ありきたりな物語でも丁寧に、わかりやすく伝える文章が書けたほうが、企業からも読者からも評価が高くなる。
基礎的な文章力に不安を感じている人は、作家志望なら小説講座、社会人ならビジネス系の文章講座を活用するのがオススメ(通信講座でOK)。
必要最低限のスキルを効率的に学べるだけでなく、仕事のやり方や業界情報なども情報収集できて一石二鳥ですね。
小手先のテクニックに踊らされていると、遅かれ早かれ痛い目をみます。
しっかりと基礎力も磨きながら、目の前の壁をひとつひとつ乗り越えていきましょう!